完全自動運転の実現に向けた高性能センシング技術
名古屋オートモーティブワールド2019:Velodyne LidarとValeoによる専門セッションより
2019/10/07
要約
 |
| Velodyne LiDAR社のライダー「Alpha Puck」をルーフに装備した車両 |
2019年9月18日~20日に名古屋で開催されたオートモーティブワールドにおける専門セッション「完全自動運転の実現に向けた高性能センシング技術」では、Velodyne Lidar社とValeo Japan社からLiDAR技術の最新情報が紹介された。
自動運転技術が進展する中で、LiDAR(ライダー)と呼ばれるセンサーが注目されている。このレポートでは、2社の講演概要について報告するとともに、LiDARの基礎知識と、類似したセンサーとしてレーダーとの違いについて説明する。
今回登壇した2社の講演内容では、センサー部品単体のビジネスに終始するのではなく、積極的に自動運転時代における新しい事業拡大を目指しているという明確な方向が示されていた。
関連レポート:
商用モビリティ:トラック隊列走行の公道実証実験(2019年8月)
自動運転車のソフトウェア・スタックについての解析(2019年6月)
人とくるまのテクノロジー展2019:自動運転社会に向けたコネクテッド技術・サービス(2019年6月)
WCX 2019: SAE World Congress Experience – 自動運転とセーフティ(2019年5月)
自動運転車(AV)エコシステムの分析(2019年4月)
オートモーティブワールド2019:実用化・高性能化が進む自動運転技術(2019年2月)

 AIナビはこちら
AIナビはこちら




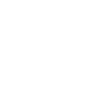






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド