Mercedes-Benz M256 直列6気筒ガソリンエンジン
Daimlerモジュラーエンジン更新計画、48Vマイルドハイブリッドシステムを採用
2018/08/31
概要
ドイツDaimlerは気筒あたりの排気量を500㏄とした、新設計のモジュラーエンジン群を2016年から順次投入し始めている。これらのエンジンは、Daimlerが新しく作った共通設計指針MPA(Mercedes Powertrain Architecture)に基づいて開発されている。
そのモジュラーエンジンの中でも、M256は同社のSクラスに搭載される主力の3Lガソリン6気筒エンジンで、Daimlerとしては、初めて48V電源部品を採用してマイルドハイブリッド化している。補機の電動化により補機駆動用のベルトを廃し、エンジン全長を短縮し、エンジンルームへの搭載性や衝突安全性を向上させている。Daimlerでは1997年に直列6気筒エンジンM104の生産を中止して以来、V型6気筒を採用してきたが、今回、V型6気筒M276の後継ユニットとして直列6気筒エンジンを投入した。 このM256は、先代V型6気筒エンジン(M276)比で約20%のCO2排出量削減と、15%以上の出力向上を実現した。
 |
 |
| M256エンジンフロント側 | M256エンジンリア側 |
出典:Daimler広報資料
関連レポート
欧州での2021/2030年のCO2規制、ディーゼル車への逆風と電動化 (2018年4月)
Daimler:2025年までに世界販売の15-25%をEVへ (2018年1月)
Mercedes-Benz OM654ディーゼルエンジン (2018年1月)
Mercedes-Benz、BMW、AudiのADAS・自動運転装備 (2017年8月)
欧州自動車メーカーのEV戦略: ダイムラーが新ブランド設立 (2016年12月)
「革新的燃焼技術」(その2):どこまで革新進むか?内燃機関エンジン (2016年12月)

 AIナビはこちら
AIナビはこちら




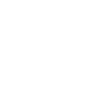






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド