人とくるまのテクノロジー展2016:トヨタ、日産、ホンダの出展
トヨタは新型プリウス、ホンダはクラリティFCVのカットボディーを出展、日産は60kWh電池を出展
2016/06/07
要 約
 3日間盛況であった「人とくるまのテクノロジー展2016横浜」の会場風景 |
本レポートは、2016年5月25~27日に開催された「人とくるまのテクノロジー展2016横浜」における、トヨタ、日産とホンダの出展を報告する。3社は、それぞれの最新の環境対応車と、それらを支える新技術を紹介した。
トヨタは、JC08モード燃費40.8km/Lを達成した新型プリウスのカットボディーを出展した。プリウスはTNGA適用第一号車で、プリウスのDNAとTNGAを融合させて誕生した低燃費パワートレインや低重心パッケージなどの特徴を紹介した。
日産は、EVリーフの電動パワートレインと、2015年12月に投入した容量30kWhのリチウムイオン電池を出展。開発中の60kWhリチウムイオン電池試作品も参考出品した。また2016年、2018年、2020年と段階を追って導入を予定する自動運転技術を紹介した。
ホンダは、クラリティ フューエルセルのカットボディーを出展。合わせて、世界最軽量のアルミ中空ダイキャスト・フロントサブフレームと、外部給電器 “Power Exporter 9000”を出展した。
関連レポート:
4代目トヨタプリウス車両分解調査(上)(2016年2月)
4代目トヨタプリウス車両分解調査(中)(2016年3月)
4代目トヨタプリウス車両分解調査(下)(2016年3月)
4代目トヨタプリウス車両分解調査:132部品の写真集(2016年5月)
多様化する電動化(下):日産は60kWh電池を開発しEV走行距離を延長(2016年2月)
FCV(燃料電池車)の開発動向と課題(2016年4月)

 AIナビはこちら
AIナビはこちら




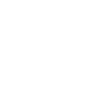






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド