外注・調達先情報PR
車載部品、自動車関連技術、ソリューションのご紹介ページです。
各製品についての資料請求、見積依頼はページ内のフォームからお問い合わせください。
※お問い合わせにはログインが必要です。ログインはこちらから
カテゴリー一覧
試作支援

株式会社インプリミス
DFA (Design for Assembly) 10 日本語版 - 製品簡略化ツール
1982年から世界で850ユーザに利用されてきたDFA(Design for Assembly) ソフトウェアバージョン10日本語版がリリースされました。
+++ DFAツールの特長 +++
* 理論最少部品基準による部品数削減
* 組立時間の算出データベース
* 組立性評価指数 (DFA指数)による組立性評価
DFMAはロードアイランド大学のブースロイド博士とデュウハースト博士により開発された手法で「組立が容易な製品設計は部品数が最少になる」という理論に基づいています。 DFMA理論の最大の成果の一つは、理論最少部品数を定義したことです。 以下の質問のいずれかに該当すると、その部品は削減できない必要部品と判定されます。 その他の全ての部品は理論上、削除可能か、もしくは必要部品と一体化できると考えられます。
1. その部品は、他の部品に対し相対的に動く必要がある? >> 例:シリンダー内のピストン
2. その部品は、他の部品と異なる材料にしなければなりませんか? >> 例:ケーブルのコネクタ 、センサ
3. その部品は、組立や分解のために他の部品と分けておく必要性がある? >> 例:電池などを交換するため蓋、部品のカバー
もし、上記の基準のいずれにも該当しないのに、設計上、別部品とする必要がある場合には、設計者は「なぜ別部品にする必要があるか」その理由の説明が求められます。 このようにして、DFA手法により、部品の一体化を進めることにより部品点数を最少化し、組立コストの低減が可能になります。
「理想的な」製品とは理論最少部品で構成される製品を指します。 この理想の製品に対する現行製品の組立性を示す評価基準であるDFA指数は、自社製品の設計の良し悪し(組立のしやすさ)を評価する指標として利用することができます。
DFA10では、ユーザが部品数低減のための分析と製品再設計に集中できるよう、ソフトウェアのユーザインターフェースが刷新されました。 製品コストの8割は図面の内容で決まるといわれています。DFAは 「組立が容易なように製品を設計することが設計者の総合目標であるべき」であるという考えのもと、生産が容易な設計を研究してきた成果です。
+++ DFAツールの特長 +++
* 理論最少部品基準による部品数削減
* 組立時間の算出データベース
* 組立性評価指数 (DFA指数)による組立性評価
DFMAはロードアイランド大学のブースロイド博士とデュウハースト博士により開発された手法で「組立が容易な製品設計は部品数が最少になる」という理論に基づいています。 DFMA理論の最大の成果の一つは、理論最少部品数を定義したことです。 以下の質問のいずれかに該当すると、その部品は削減できない必要部品と判定されます。 その他の全ての部品は理論上、削除可能か、もしくは必要部品と一体化できると考えられます。
1. その部品は、他の部品に対し相対的に動く必要がある? >> 例:シリンダー内のピストン
2. その部品は、他の部品と異なる材料にしなければなりませんか? >> 例:ケーブルのコネクタ 、センサ
3. その部品は、組立や分解のために他の部品と分けておく必要性がある? >> 例:電池などを交換するため蓋、部品のカバー
もし、上記の基準のいずれにも該当しないのに、設計上、別部品とする必要がある場合には、設計者は「なぜ別部品にする必要があるか」その理由の説明が求められます。 このようにして、DFA手法により、部品の一体化を進めることにより部品点数を最少化し、組立コストの低減が可能になります。
「理想的な」製品とは理論最少部品で構成される製品を指します。 この理想の製品に対する現行製品の組立性を示す評価基準であるDFA指数は、自社製品の設計の良し悪し(組立のしやすさ)を評価する指標として利用することができます。
DFA10では、ユーザが部品数低減のための分析と製品再設計に集中できるよう、ソフトウェアのユーザインターフェースが刷新されました。 製品コストの8割は図面の内容で決まるといわれています。DFAは 「組立が容易なように製品を設計することが設計者の総合目標であるべき」であるという考えのもと、生産が容易な設計を研究してきた成果です。
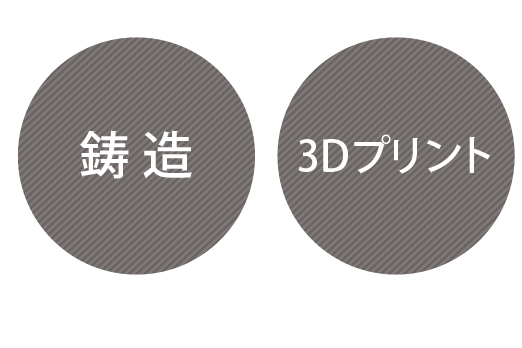
株式会社 JMC
短納期試作!何でもご相談ください、最適な工法をご提案いたします。
どのような工法で作れば良いのか、お悩みではありませんか?
JMCでは鋳造・3Dプリンター・注型・切削などの造形方法から、CTスキャン・非接触測定などの検査測定まで、試作に関するノウハウがあるので、なんでも対応可能です。
まずは、あなたの作りたいものをお伝えください。最適な工法をご提案いたします。
JMCでは鋳造・3Dプリンター・注型・切削などの造形方法から、CTスキャン・非接触測定などの検査測定まで、試作に関するノウハウがあるので、なんでも対応可能です。
まずは、あなたの作りたいものをお伝えください。最適な工法をご提案いたします。







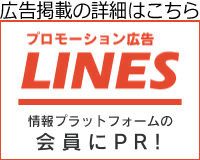
 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド