NCAP(新車アセスメントプログラム)の概要と動向(2)
衝突時乗員保護や自動ブレーキ(AEB)などのテスト項目と各NCAPの実施状況
2020/06/10
要約
NCAP (New Car Assessment Programme 新車アセスメントプログラム)の評価項目は、開始当初の米国では衝突テストによる衝突時乗員保護性能を中心としていたが、その後、他のNCAPが開始されるにつれ、子供の保護、歩行者保護など少しずつ内容が拡がった。更に自動ブレーキ(AEB)による交通弱者の保護や、推奨される安全デバイス装備などの先進テクノロジーも評価する例が増え、これらの各項目にそれぞれ重み付けして、総合的な評価とするNCAPが多くなっている。
今回のNCAPレポートは樋口和雄氏の協力を得て、前稿のPart1では、各NCAPの特徴、問題点、そしてEuro NCAPの「Roadmap2025」に代表される将来動向を解説。本稿のPart2では、自動ブレーキ(AEB)などの新項目を含むNCAPテスト法の詳細と各NCAPの実施状況について説明する。
関連レポート:
NCAP(新車アセスメントプログラム)の概要と動向(1)世界の主要NCAPプログラムの総合評価体系の概要と特徴 (2020年5月)
2020 AV/ADAS 安全基準と規制の現状 (2020年5月)
NCAP(新車アセスメントプログラム)の概要と動向 (2017年12月)

 AIナビはこちら
AIナビはこちら




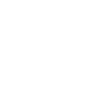






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド