トヨタのITS:世界初の路車間・車車間通信を新型プリウスなど3車種に設定
刻々と変化する交通情報をリアルタイムで伝達し、自律型安全装備を補完
要 約
 日本の官民が推進する「協調型ITSサービス」、下段中央のITSスポットサービスは既に実現している、上段左の次世代DSSSは今回トヨタが実現した技術(SIDS (Signal Information Drive System) は除く)、その他3項目およびSIDSはこれから実用化される技術(資料:ITS Japan) |
本レポートは、トヨタが2015年後半に日本で発売した3車種、新型Prius、マイナーチェンジしたCrown Majesta、Royal/Athleteに搭載したITS Connectについて報告する。
既に実用化されているITSスポット(高速道路に設置された安全運転支援システム)やDSSS(Driving Safety Support Systems/一般道路に設置)は協調型ITS(Cooperative Intelligent Transportation Systems)と呼ばれる。クルマに搭載したセンサーでは捉えきれない情報を取得することで自律型の安全運転システムを補完し事故低減に貢献している。トヨタが今回採用したITS Connectは、路車間・車車間通信を利用し、協調型ITSの従来レベルを超えて、刻々と変化する交通情報をリアルタイムで把握・伝達することで、より精緻な安全対策を実現する。
ITS Connectは、ITS専用周波数(760MHz)を使用し、路車間通信により「右折時注意喚起」など交差点での安全対策を、また車車間通信を利用した「通信利用型レーダークルーズコントロール」を開発した。さらに次の段階として、車車間通信を利用し出会い頭の衝突を防止するシステムや、歩行者とクルマが通信する技術の開発を進めている。
これらのシステムは、例えば車が支線から本線に合流する場合などでの車の動きの予測を可能にするので、将来の自動運転における運転知能の実現にも不可欠な技術であるとしている。
課題としては、路車間通信の路側インフラが整備される交差点は、2016年3月末で東京都と愛知県の約50箇所にとどまり、全国に配備するには膨大なコストがかかることが見込まれている。トヨタは、この機能を搭載する車両を発売することが、路側インフラ設置の促進にも貢献するであろうとの思いで、設定車種の発売に踏み切ったとしている。
なお車車間通信を利用する技術として、Daimlerは、2013年に発売した新型Mercedes-Benz S-Class、2016年に発売した新型E-Classに、スマートフォン間で通信するCar-to-X communicationを設定した。まず早期に実現できるスマートフォン間の通信システムを採用したが、別途専用の車車間通信システムの開発も進めている。
ホンダは、Wi-Fi通信で車と車、車と専用スマートフォンアプリを持つ歩行者が互いに通信する技術を確立した。
関連レポート:
トヨタ:「つながる技術」の取組みを加速、車載通信機「DCM」の搭載を拡大(2016年3月)

 AIナビはこちら
AIナビはこちら




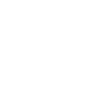






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド