自動運転の2つのトレンド:レベル3の高速道路型とレベル4の生活道路型
Autonomous Vehicle & ADAS Japan 2017から
要約
 |
| 高速道路型と生活道路型の自動運転が近く実現する |
2017年5月に、”Autonomous Vehicle & ADAS Japan 2017”が東京で開催された。本レポートは、同講演会での、インテル 政策・事業開発ディレクター兼名古屋大学客員准教授 野辺 継男氏による「自動運転車の将来の大変革を巻き起こす2大海外動向」と題した講演の概要を報告する。
野辺氏によると、今後の自動運転の進展については、二つの大きな動向がある。まず2020年頃に、高速道路でのレベル3の自動運転が導入されるが、これは①既存自動車産業による、ADAS延長線上での継続的イノベーションの成果である。
一方、生活道路型(郊外型)レベル4の自動運転に必要な技術がここ2~3年で急速に進展して、同じ2020年頃に導入される見込み。ここにはラストワンマイル需要への対応や、ライドシェアやカーシェアが含まれる。高速道路走行に比べはるかに多様な障害物への対応が必要になるが、ディープラーニングの進化により、AIが車の走り方を指令して走行することが可能になりつつある。また3次元地図も限定された地域について作成するので投資額が小さくて済む。これは上記①とは異なり、②Web系企業による破壊的なイノベーションをもたらすものである、と野辺氏は強調している。
将来、自動車業界のモノづくり産業のピラミッド構造とデータドリブン産業のピラミッド構造が合体すると予測されるが、そのときにはサービス・プロバイダーやIT技術を提供する企業がOEMの上にくることもありうるとされる。欧米のOEMは、自らがサービス・プロバイダーになろうとする動きを加速させている。
関連レポート:
米国NHTSA:自動運転車へのガイダンスを発表(2016年11月)
Ford:2021年にドライバーレス車を量産し、ライドシェアリングに投入(2016年12月)







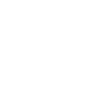






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド