【ものづくり】自動車の軽量化を促進するプラスチック部品・材料
内燃機関、電動車のパワートレイン、ドアトリムなどの採用事例
要約
自動車業界における重要なテーマの1つに軽量化があげられる。自動車の軽量化を促進している材料の1つがプラスチックであることは間違いない。本稿では、近年ますます重要性が高まっている自動車用プラスチックの技術動向について紹介する。最初に自動車に使用される各種プラスチックの特性や採用動向などを一覧表にまとめ、続いて最近の材料開発や加工技術の動向を紹介する。
プラスチックを使用した自動車部品は、非常に多くの車両部位に使用されているが、本稿では代表的なパワートレイン部品および内装部品のプラスチック用途例について、様々な展示会で撮影した画像を用いて解説する。ICE(内燃機関)ならびにEV、HV、FCVなど電動車のパワートレインに採用されているプラスチック部品・材料、ドアトリムの素材や各種内装部品に採用されているプラスチック材料などを紹介する。
 |
 |
 |
| プラスチック材料はバッテリーの軽量化にも貢献 | 複雑な形状のインテークマニホールド | 耐衝撃性、デザイン性も求められるドアトリム |
本稿は安田ポリマーリサーチ研究所の安田武夫所長の協力により、同氏がシーエムシー・リサーチ「自動車用プラスチック部品の開発・採用の最新動向 2018」で紹介した資料をもとに、最近注目されているプラスチック関連技術の動向も加えて報告する。また次回レポートでは接合・接着などプラスチック加工技術の動向を取り上げる。
関連レポート:
エヌプラス2018:一歩先行く自動車部品材料 (2018年10月)
第1回 名古屋オートモーティブワールド2018 (2018年9月)
人とくるまのテクノロジー展 2018:軽量化加工技術と樹脂材料 (2018年5月)
TECHNO-FRONTIER 2018:自動車産業の課題に応える加工技術 (2018年4月)
オートモーティブワールド2018:異種材料の接合、高機能プラスチックの展示 (2018年2月)
オートモーティブワールド2018:CFRP部品・プラスチック成形加工技術の展示 (2018年1月)

 AIナビはこちら
AIナビはこちら




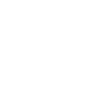






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド