トヨタのEV/PHV戦略:マツダとEVを共同開発
中国市場では2018年にPHVを現地生産、EVを2019年にも投入予定
要約
 |
| 2017年8月に、トヨタとマツダがEV共同開発など業務資本提携で合意 |
本レポートは、トヨタのEV/PHV戦略について報告する。
トヨタとマツダは、2017年8月、業務資本提携に関する合意書を締結した。EVを共同開発するとともに、米国で30万台規模の生産能力を持つ完成車合弁工場を建設する計画。
ハードウェアとソフトウェアを含めて、軽自動車から小型トラックまでをカバーするEVの基本構造の技術(以下「プラットフォーム」と呼ぶ)を共同開発する。車両自体は、それぞれが独自色をもって開発し、マツダは2019年、トヨタは2020年に投入するとされる。
トヨタは、究極のエコカーとしてFCV開発に注力し、EVは航続距離の課題から早期の本格普及は困難としていた。しかし、ゼロエミッション車普及に向けた規制強化が各国で急速に進んでいる現状を踏まえ、FCVとともにゼロエミッション達成の選択肢となるEVの早期投入が可能となる体制構築を進めている。
各国でガソリン、ディーゼル車の販売禁止や、EV販売の強化に向けた発表が相次いでいる。英国・フランスは2040年までに内燃機関を搭載する車両の販売を終了すると発表。インドはさらに早く2030年に終了する方針。また、VW、Daimlerなどが、EVラインアップや商品構成の大幅強化を発表した。
米国カリフォルニア州では、2018年モデルイヤーからZEV規制を強化し、ハイブリッド車(HV)はZEV(Zero Emission Vehicles)の対象外となった。一方、California Air Reserves Board (CARB)は、2025MYのZEV規制適合車の約6割はPHVになると予測している(残りはEV/FCVになる)。新開発するEVとともに、PHV(現在はPrius Prime 1車種)もZEV規制達成に大きな役割を果たす。
中国ではNew Energy Vehicle (NEV:EV/PHV)市場が拡大し、中国政府は2018年以降に、自動車メーカーに一定割合のNEV生産を義務付けるとされる。NEV規制も、HVを環境対応車に含めていない。トヨタは、中国市場には、PHVを2018年に導入すると発表している。次いでEVを他地域よりも早く2019年にも投入する計画とされる。
またトヨタは、2016年12月に、社内ベンチャー組織「EV事業企画室」を発足させた。これまで同企画室で進めてきたこととマツダとの共同開発を融合させ、EV開発を加速させる。
関連レポート:
欧州自動車メーカーのEV戦略: ダイムラーが新ブランド設立(2016年12月)

 AIナビはこちら
AIナビはこちら




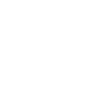






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド