Daimlerと日野のFCV開発と水素社会実現に向けた取り組み
第13回オートモーティブワールド2021のセミナー講演より
2021/02/17
要約
 |
| 政府の緊急事態宣言期間中であったが、新規性が高く重要なトピックとあって多くの聴講者を集めていた。 |
本レポートは、第13回オートモーティブワールド(会期:2021年1月20~22日、会場:東京ビッグサイト)で開催されたセミナー講演の中から、Daimler Truckと日野のFCV開発への取り組みに関する内容を紹介する。
ダイムラー社の自動車および定置型向けモジュラー燃料電池エンジン
講演者:Prof.Dr. Christian Mohrdieck, Chief Executive Officer, Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH
Daimlerグループにおける直近の動向と今後の方針を「開発の歴史」、「FC技術の新しいアプローチ - モジュラーFCエンジン」、「FC応用分野の拡大とDaimlerの電動化計画」の3パートにまとめ説明する。
商用FCVの実用化に向けて
講演者:通阪 久貴 氏 日野自動車株式会社 先進技術本部長
日野は環境チャレンジ2050を発表し、そのなかでトラック・バスのCO2削減を重要な課題と位置づけている。講演では「日野の環境対応技術開発の経緯」、「今後の電動化方針」、「大型商用車におけるFCの利点」、「具体的なFCV技術」、「残る課題」について述べる。
関連レポート:
カーボンニュートラルな貨物輸送への道筋(2020年12月)
SAE China 2020 (2):商用車の電動化(2020年11月)
燃料電池商用車:トヨタが中国大手OEMとFCシステムを共同開発(2020年7月)
重量車(トラック、バス)の電動化に関する技術動向(2020年6月)
Daimler:電動化への投資を優先、投資総額を抑制しキャッシュを保持(2020年5月)
スマートエネルギーWeek2020:電動車関連技術(1)(2020年3月)







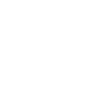






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド