日産リーフ分解調査(その3):カットボディーの展示取材報告
減速機、インバータ、電動型制御ブレーキ、空調システムなど
2012/11/12
要 約
埼玉自動車大学校の学園祭「埼自大祭」が10月27~28日に開催され、同校学生が製作した「日産リーフ・カットボディー」が展示された(車両は「次世代自動車支援センター埼玉」が所有し同大学校に貸与したもの)。またカットボディー作成作業中に、リーフの基幹部品について、9月に掲載した下記のMarkLinesレポートより一歩分解が進んだ状態で取材する機会を得た。
これらの概要を、「日産リーフ分解調査(その3)」として報告する。従って、掲載した写真は、カットボディーの一部である場合と、分解された状態の部品とがある。
また、赤色に塗った部分はカット(切断)した断面を示す。青色は水の貯蔵または水路を示している。
| 関連レポート: | 日産リーフ分解調査(その2):主要部品の分解展示報告(2012年9月掲載) |
| 日産リーフ分解調査(2012年2月掲載) |
※写真はクリックすると拡大されます。

 AIナビはこちら
AIナビはこちら




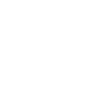






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド