日産:自動運転時代を見据えたコネクテッド戦略
MicrosoftのConnected Vehicle Platformを採用、2022年に完全自動運転を目指す
要約
 |
| DeNAと共同で実証実験を開始した無人運転車Easy Ride(資料:日産) |
本レポートは、日産自動車株式会社 コネクテッド・カー&テレマティクス開発グループ、兼AD&ADAS先行開発部HDマップ開発グループ、兼コネクテッド・カー&自動運転事業本部 主管 村松寿郎氏によるTU Automotive Japan 2017(2017年10月開催)での講演、「自動運転時代を見据えたコネクテッド・カー」を中心に、日産の自動運転に繋がるコネクテッド戦略の概略を報告する。
日産は、1)EVに代表されるNissan Intelligent Power、2)自動運転に代表されるNissan Intelligent Driving、3)Connected Carに代表されるNissan Intelligent Integrationの3項目から成るNissan Intelligent Mobilityを掲げている。日産は、これまで培ってきた3つの技術を組み合わせることにより、未来の車はelectric、autonomousそしてconnectedになるとしている。2022年に完全自動運転(無人運転)を目指す。
Renault-日産は、MicrosoftのクラウドAzureベースのConnected Vehicle Platformを採用する。同Platformは、最先端のナビゲーションシステム、遠隔からの車両状況の把握、無線通信によるプログラム更新(OTA)などを通じて自動運転に貢献する。同時に、運転から解放される完全自動運転車において、外部へのモバイル接続や車両向けサービスにより、乗員の車内の時間の過ごし方を充実させることも目指している。
日産は、自動運転車の遠隔監視システムSeamless Autonomous Mobility(SAM)を、2017年末からDeNAと共同で開始した無人運転サービス「Easy Ride」の実証実験に導入する。2018年1月には、SAMを共同開発したNASAと、さらにテストを重ね完成度を高めていくと発表した。究極のNissan Intelligent Integrationであり、自動運転を早期に実現するためのキーになるとしている。日本と米国で、遠隔監視システムを、公道での無人運転実証実験の条件とする動きもある。
村松氏は、2020年以降徐々に通信の5G化も進み、車が新たな機能・特性を持ち、新たなサービス、ビジネスが生まれてくるであろうとの展望を示した。
日産は2018年1月、Continental AG、Qualcommなど5社と共同で、日本初のセルラーV2Xの実証実験を2018年から開始すると発表した。5G技術が利用可能となり次第、タイムリーにサービスを提供したいとしている。
関連レポート:
Renault、日産、三菱自:2022年に1,400万台販売、売上高2,400億ドルを見込む (2017年10月)
東京モーターショー2017:日産・ホンダ・三菱自の出展 (2017年11月)







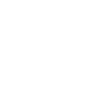






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド