中国民族系自動車メーカーのメガ・プラットフォーム戦略
車種当たりの採算性改善で、混戦激化の価格競争からの生き残りを模索
背景:なぜ、中国民族系メーカーはメガ・プラットフォームに向かうのか?
| 図1:2000年以降の中国基本型乗用車市場(万台・%) |
 |
| 資料:『汽車工業経済運行報告』各年版より筆者作成。 |
2000年前後から、中国の乗用車産業において、外国の技術導入ではなく、自主開発・自主ブランドを売りにする中国企業が多数出現するようになった。それ以降、2010年までは、セダンとハッチバックから構成される主力セグメントの基本型乗用車市場は、中国民族系が低価格車を武器に台頭し、従来から人気の高かった日系車と共に、独VWの一社独占状態に終止符を打ったのである(図1参照)。
2010年以降は、基本型乗用車市場において、外資系メーカーの低価格車種の持続的投入によって、従来の高価格車は外資、低価格車は中国系という棲み分け構造が崩れ、混戦状態に陥った。しかし、ブランド力では外資に劣る中国民族系メーカーにとって、外資系の製品ライナップの下方浸食は、自らの生存領域が圧迫される事態をもたらし、収益力の低減につながった。その打開策として考案されたのは、商品戦略の軸足を、低価格乗用車市場から別の空白市場、すなわち廉価な小型SUV市場へ移す試みである。セダンからの乗り換え需要と相まって一気に新市場を掘り起こし、その試みが奏功したのである。
ただ、外資メーカーが早期に、廉価な小型SUV市場への下方浸食することも予想できる。そのため、この新市場における民族系メーカーの製品の優位性は従来の基本型乗用車市場で経験したほど長くは続かないこともあり得る。そのため、こうしたジレンマからの脱出を目指して、注目され始めたのはメガ・プラットフォーム戦略である。
また、2010年以降について、日系/中系メーカーの消沈と対照的に顕在化したのはドイツVWの復権である。部品の現地調達、開発の現地移管などの通常の手段のほかに、VWが積極的に推進するMQB戦略は、「なぜVWだけが復権したのか?」への回答にヒントを与える。
2013年にMQBベースの新車の生産能力は100万台という大台に達し、2016年には400万台に達する見通しである。そのうち、中国においては、一汽-VWの長春、佛山、青島、天津工場と上海VWの上海安亭、南京、寧波、長沙工場に、MQBベースの新車を投入し、世界のMQBベース車の生産計画に占める中国の比率を大幅に引き上げる。これによって、単一車種のグローバル採算性を段階的に向上させながらも、多様に変化する中国市場においてもフレキシビリティと採算性の同時達成を創出でき、低価格車市場への浸透もいっそう容易になると予測される。
他方、外資系の売れ筋のモデルをベンチマークして、低価格車として市場投入する戦略を中国民族系メーカーは長らく取ってきた。彼らにとって、外資系車種の低価格化は従来の成長領域が圧迫され、一転して死活問題と化したため、近年メガ・プラットフォームへの転向が急がれている。
民族系メーカーでは、規模の経済性を維持するため、売れない車種でも脈々と延命させる傾向がある。そのため、歴史の長いメーカーのほうが、売れない車種をより多く持つ傾向となり、採算性と規模経済性維持との間のジレンマがいっそう深刻である。言い換えれば、こうしたメーカーこそ、メガ・プラットフォームへの転向に対するモチベーションが高いと言えよう。
関連レポート







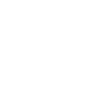






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド