次世代エンジン開発
止まらない進化、マツダのこだわり
2016/02/04
要 約
 (マツダ資料から) |
2016年1月13日から3日間、東京ビッグサイトにて第8回AUTOMOTIVE WORLD2016が開催された。展示会では昨年より145社増加、781社が自動車用部品等を展示。同時に各種専門セミナ-、記念講演が多数開催され、自動車の軽量化、デザイン、電動化、エンジン技術、センサー技術等のトピックスが議論された。本稿はセミナ-「次世代エンジン開発 止まらない進化」(Auto-7)の内容から内燃機関の将来動向を報告する。
2020年以降も自動車用の内燃機関は進化を続け、欧州・米国・中国・日本で継続して使われていくと予測されている。地球温暖化抑制の為、自動車からのCO2排出量の削減、熱効率の高いディーゼルエンジンの活用とその排気処理課題、排気試験モードと実走行問題、HCCI(Homogeneous-Charge Compression Ignition:予混合圧縮着火)は本当に実現できるのか?、日米欧で異なるハイブリッド車及び電動化の行方、究極と言われるFCV(燃料電池車)等、自動車用の内燃機関を取り巻く課題は際限がない。
関連レポート
・人とくるまのテクノロジー展2015:日本メーカーの最新パワートレイン技術
Post2025年の乗用車用パワートレーンの主流は?(日本メーカー編)
Post2025年の乗用車用パワートレーンの主流は?(欧州動向編)

 AIナビはこちら
AIナビはこちら




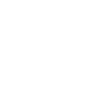

 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド