人とくるまのテクノロジー展2015:Post2025年の乗用車用パワートレーンの主流は?(日本メーカー編)
トヨタ、日産、ホンダ、マツダが考える内燃機関の将来技術
2015/06/15
要 約
人とくるまのテクノロジー展2015(於パシフィコ横浜、2015年5月20~22日)の自動車技術会2015年春季大会フォーラムで、「Post 2025年の乗用車用パワートレーンの主流は?」と題して、産官学の各方面から講演があった。今回その中から、自動車メーカー4社の講演内容を紹介する。
背景には、大気汚染、地球温暖化への対応として、今後CO2 削減の必要性がさらに高まり、そのために様々な手段を講じていく必要が生じている。そういった状況の中、パワートレーンの将来像としては、4社ともにEV、PHVが増加していっても依然として内燃機関がなくなることはないとしている。したがって、内燃機関のCO2 削減は、将来にわたって継続的に進めていかねばならない重要な技術課題である。今回の講演での、自動車メーカー4社が考える将来の内燃機関の技術の方向性を解説する。
関連レポート
人とくるまのテクノロジー展2015:トヨタとホンダが直噴ターボエンジンを出展
人とくるまのテクノロジー展2015:部品メーカーの出展(上) トヨタ ミライ搭載部品
人とくるまのテクノロジー展2015:マツダデミオの最新車体技術
人とくるまのテクノロジー展2015:自動車メーカーの安全装備と自動運転の出展

 AIナビはこちら
AIナビはこちら




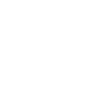






 日本
日本 米国
米国 メキシコ
メキシコ ドイツ
ドイツ 中国 (上海)
中国 (上海) タイ
タイ インド
インド